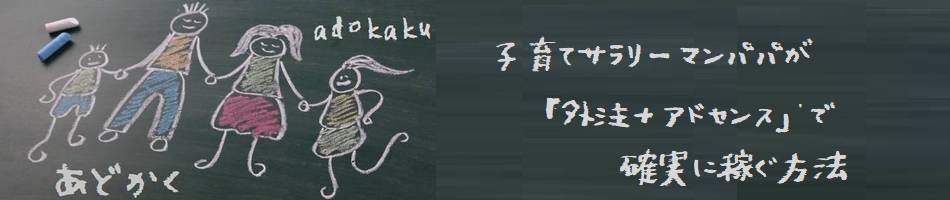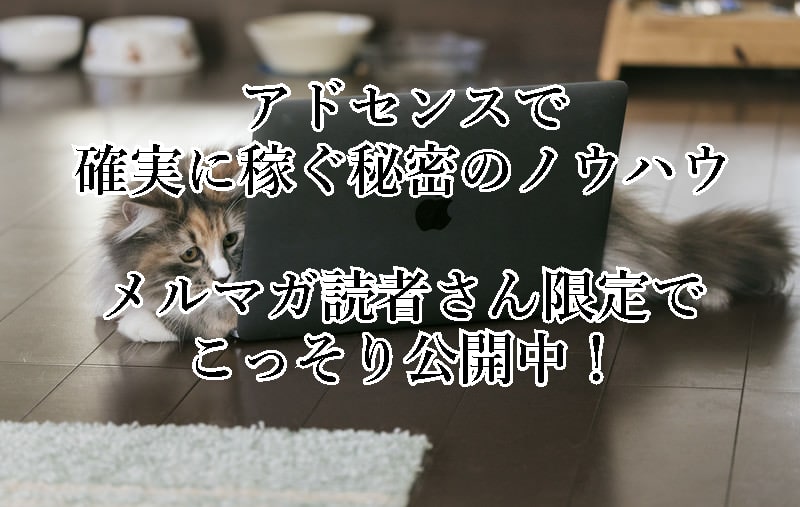こんにちは。このページを開いてくださって、本当にありがとうございます。
もし今、あなたがブログのことでちょっとでも迷ったり、「続けられるかな…」「これって意味あるのかな…」って立ち止まりそうになっているとしたら、その気持ち、すごくよくわかります。
なぜなら、僕もまったく同じ場所に立っていたから。
このプロフィールでは、そんな僕の過去や今、そしてブログにかける想いをお話します。決して順風満帆ではなかったけど、それでも続けてきた理由。もし共感してもらえたら、それだけでこの文章には意味があると思っています。
“どこにでもいるパパ”だった僕が、ブログを始めた理由
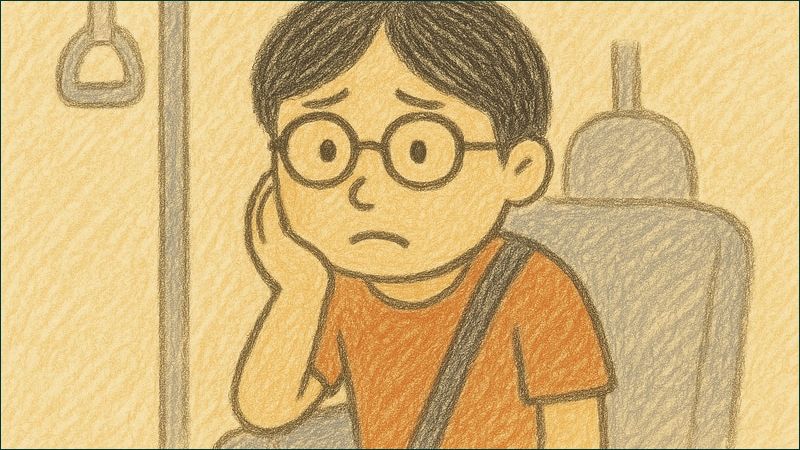
僕は、どこにでもいるような普通の会社員です。朝は7時に家を出て、ぎゅうぎゅうの満員電車に揺られながら通勤し、
駅に着いたら慌ただしくコンビニでおにぎりとコーヒーを買って職場へ。昼はほとんど机にかじりついたまま仕事。帰宅は夜9時を過ぎることも珍しくなくて、
子どもたちの寝顔しか見られない日もたくさんありました。
それでも休日になると、少しでも家族との時間を大切にしたくて、
- 妻と一緒にスーパーへまとめ買いに出かけたり、
- 息子とNintendo Switchでマリオカート対決したり、
- 娘の気分に左右されながらも、なんとか会話のきっかけを探したり
そんな、なんでもないけど温かい日々。だけどあるとき、ふとした瞬間に、心の奥から疑問が浮かんできたんです。
「このままで、10年後も笑っていられるのかな…?」
今の仕事に大きな不満があるわけじゃない。
でも、どこかずっと「この働き方はいつか終わるかもしれない」という不安を抱えていた。実際、身近で早期退職やリストラの話を聞くようになっていたし、
「自分も他人事じゃない」と思わずにはいられませんでした。
それに、子どもたちが成長するにつれて思ったんです。
「“家族のために”働いてるのに、なんで“家族といる時間”がこんなに少ないんだろう?」って。
当時、世の中では“副業解禁”とか“脱サラ成功!”なんて言葉が飛び交っていて、
ちょっとだけ羨ましく感じたのも事実です。でも僕には特別なスキルも資格もない。
そんなときに出会ったのが「ブログ」という選択肢でした。
最初は、ほんの小さな好奇心でした。「これなら自分にもできるかもしれない」と思っただけ。
でも書き始めてみると、思いがけず、心の奥にあった“伝えたいこと”が言葉になってあふれてきたんです。
仕事で溜め込んでいた想いや、父として感じていた焦りや喜び、
自分でも気づいていなかった本音までもが、キーボードを打つ指先から少しずつ零れていきました。
書くことで整理される気持ち。そして、ポツリと届く「読んだよ」「わかる、その気持ち」というコメント。誰かと“繋がれた”実感が、心をじんわりと温めてくれました。
それは、僕にとって単なる副業じゃなく、“自分を取り戻す時間”になっていったんです。
9年やっても、ずっと“中途半端”だった
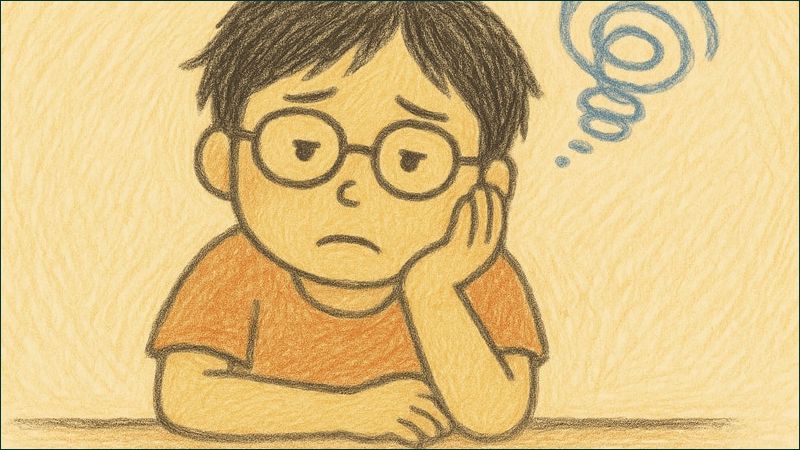
正直、思ってたより全然うまくいきませんでした。「誰かの役に立つ記事を」と思って書いても、アクセスは1日10以下。検索順位は100位以下。一生懸命書いた記事が、まったく読まれずに埋もれていく感覚って、ほんとうに心が削られます。まるで、砂漠に水をまいているようなむなしさ。
「こんなに頑張っているのに、誰にも気づかれない」
「何のために書いてるんだろう?」
そんな感情が、毎日のように胸の中をぐるぐると巡っていました。
そして、ふと気づくんです。「今日もまた、書くのが怖いな…」って。書くこと自体が怖くなる。指が止まる。そんな自分に嫌気がさして、自己嫌悪のループに陥る。
途中、何度もやめようと思いました。「どうせ僕には才能がないんだ」「他の人みたいに上手にできないし…」
SNSでは、どんどん成果を出している人たちの投稿が流れてきて、
それを見るたびに、自分がどれだけ“できていない”かを突きつけられるようで、
スマホをそっと伏せるしかない夜もありました。
そんな風に思ってしまって、数ヶ月放置してしまった時期もあります。
「もういいや」と思って、WordPressの管理画面を開くことすら怖くなった時期もありました。
でも、それでもやめなかったのは、「少しずつでも、変わっていきたい」と思っていたから。そして、諦めたらすべてがゼロになってしまう気がしたから。
小さな変化でいい。昨日よりほんの1ミリだけ進めたら、それでいい。例えるなら、毎日ほんの1円貯金するような感覚。
すぐに大金にはならないけれど、ちゃんと“自分への投資”にはなっていると信じていました。
そう信じて、またパソコンに向かって、キーボードを叩きました。深夜、家族が寝静まったあと、キッチンの片隅でコーヒー片手に、静かにカタカタとタイピングするその時間が、
いつしか“心のリセット時間”にもなっていました。
実際、3歩進んで2歩下がる、いやむしろ5歩下がるような日もありました。記事を10本書いても1本も読まれなかったり、テーマを変えても成果が出なかったり、
「ああ、また無駄に時間使っちゃった…」とため息をついた夜もあります。
でも、不思議と「ゼロには戻っていない」と思えたんです。過去に書いた記事が、たまに誰かの検索に引っかかって、ぽつんとアクセスが増えたり。「参考になりました」というたった一言のコメントが、何よりの救いになったり。
そういう小さな希望が、絶望をぎりぎりのところで食い止めてくれていました。
ブログは“続けること”が何よりの才能なんだ。
そんな風に、自分に言い聞かせながら、今も前に進み続けています。
変化のきっかけは、“AI”との出会い
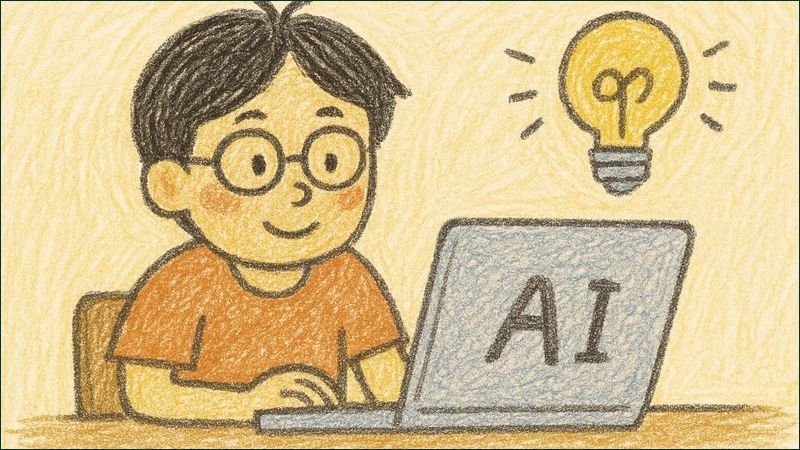
そんな僕にとって、大きな転機になったのが「AIとの出会い」でした。
それまで僕は、外注という手段にも挑戦していました。「自分ではなかなか記事が書けない。だったらプロに頼んでみよう」
そんな気持ちで始めた外注ライターさんとのやり取り。最初はワクワクしていたんですが、実際には、
・思ったような文章が来ない・何度も修正のやり取りが必要になる・時間がかかりすぎて、どんどんモチベーションが下がっていく・そのうちに「結局、自分でやった方が早いのでは?」という疑問にぶつかる
そんな日々の連続でした。
それに加えて、外注の管理に時間を取られるぶん、
僕にとって何より大切な「家族との時間」が削られていくのが、すごくつらかったんです。せっかく副業をやっているのに、家庭の空気がピリついてしまうようでは本末転倒だと感じていました。
そんなときに、ふと試してみたのが“AIライティング”でした。
「まあ、ちょっと試してみようか」くらいの軽い気持ちだったのに、結果は想像以上。AIと対話しながら記事の構成を練ったり、文章の流れを整えたりしていくうちに、
「あれ?これ、自分の思ってることがちゃんと形になってる…」と感じるようになったんです。
それまでは、頭の中でモヤモヤしていたアイデアをうまく言語化できずに止まっていたのが、
AIの提案にヒントをもらうことで、スムーズに流れ始めた感覚がありました。
「記事作成=しんどい作業」だったのが、「伝えたいことを、ちゃんと形にできる」時間に変わっていったんです。
これはもう、僕にとって革命的でした。“自分の中にある想い”が、AIの手を借りることで、うまく言葉として表に出てくる。この感覚を知ってから、書くことが楽しくなりました。
さらに、AIと一緒に作った記事を読んだ方から「すごく読みやすかった」「心に響きました」という声をいただくことも増え、
「伝わるって、こんなに嬉しいことなんだ」と実感するようになりました。
書くことが“義務”じゃなく“喜び”に変わった。そのきっかけをくれたのが、間違いなくAIだったと思います。
そして、今では「どうやったらAIと一緒に、より良い文章が作れるか?」を考えることが、
僕のライティングの中でのひとつのテーマにもなっています。
もちろん、すべてをAIに任せきりにするわけじゃありません。でも、“ひとりじゃない”と思えるだけで、パソコンに向かう時間がずっと心強くなったのは間違いありません。
AIは、僕にとって“効率のためのツール”というより、“相棒”のような存在になっています。
失敗から学んだこと、遠回りして見えた景色
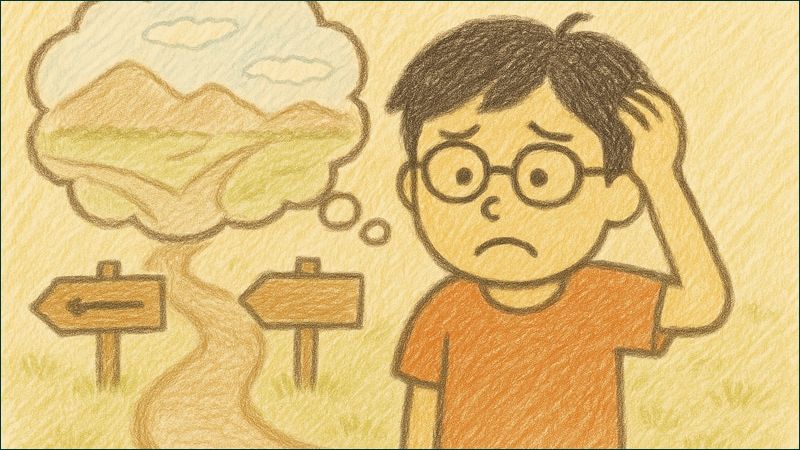
9年やってみて、ようやく気づいたことがあります。それは、「正解」は人それぞれ違うってこと。
ブログを始めた当初は、「これが正しい」と言われる情報を片っ端から試しました。
「文字数は〇〇文字がベスト」「内部リンクをこう貼るとSEOに強い」「トレンドに乗れば爆伸びする」など、いわゆる“王道”と呼ばれるノウハウを信じて、ひたすら実行していました。
でも、うまくいかなかった。というより、「合わなかった」というのが正しいかもしれません。
どれも確かに“正しい”方法なのに、自分の心がどこか置いてけぼりになっていたんです。
僕はセンスもないし、勢いでガッと稼げるタイプでもない。記事のネタ探しに何時間もかけてしまったり、1つの記事を書くのに3日かかったり、まったく“要領がいい”タイプではありません。
だけど、コツコツ続けることだけは、誰にも負けないかもしれない。「昨日より今日、ちょっとだけでも進めたらOK」と思える粘り強さだけはあったと思います。
それが、唯一の自信になっています。
途中、遠回りもいっぱいしました。「SNS頑張るぞ!」と意気込んでアカウントを開設しても、投稿が続かずにすぐに放置。「これが稼げる!」と誰かが言っているテーマに飛びついて、まったく興味がわかずに筆が止まり、また方向転換。
試しては失敗し、軌道修正をして、また試して…。
そんな繰り返しの中で、「誰かの正解」じゃなく「自分のやり方」を少しずつ見つけていった気がします。
でも、そんな失敗のひとつひとつが、今の“やさしいノウハウ”になっています。「これは自分には合わなかったけど、こう変えたら続けられた」
「これは多くの人には効率的だけど、時間がかかってもこうした方が心地よかった」
そんな“ゆるさ”や“実感”が、このブログの芯になっています。
だからこのブログでは、「初心者がゼロから続けられる」ことにこだわって書いています。たくさんのノウハウに振り回されて、前に進めなくなっている人にこそ、届いてほしいと思っています。
「がんばってるのに報われない」「時間だけが過ぎていく」「自分だけ、うまくできない気がする」
そんな風に感じている人が、少しでも前向きになれるような。そんな記事を届けたいと思ってます。
そして大事にしているのは、“結果より過程”を味わうこと。「うまくいった・いかなかった」よりも、「今日は自分らしく書けたか?」「自分の気持ちをちゃんと整理できたか?」そんな問いを持てるようになってから、ブログは“戦い”じゃなく“対話”になりました。
“もっと成果を出さなきゃ”と自分を追い込むより、
“自分のペースでいいよ”と声をかけてあげられるようになってから、
文章にも、生活にも、すこしずつ余白ができたように感じています。
遠回りだったけど、そのぶん、たくさんの景色が見られました。そして今、それを道しるべとして誰かに渡せたら、それが何より嬉しいことです。
今の僕と、そしてあなたへ

今の僕は。
娘の高校受験にドキドキしながら、ちょっとした会話の端々に親としての緊張がにじみ出るような日々を過ごし、
一方で、息子からは「今日の算数わかんない!」「ゲームやろう!」と呼ばれながら、あっちでもこっちでも親業をこなしています。
会社では相変わらず会議や報告に追われ、少し気を抜くとメールが山のように溜まる。
それでも空いた時間を見つけて、ブログのネタを考えたり、記事の構成を練ったり
気づけば、父として、会社員として、そして何より“書く人”として、地味だけど着実に前に進んでいます。
でも、そんな僕でも、たまには心がぽきっと折れそうになることがあります。何を書いても手応えがなかったり、自分の発信に意味があるのか疑問を持ったり、
「これって本当に誰かの役に立ってるのかな?」と不安になる日もあります。
それでも、そんなときこそ「書く」ことで自分の気持ちを取り戻せる。タイピングの音が、心のモヤモヤを少しずつ吐き出してくれるような感覚があるんです。そして、記事を読んでくれた誰かから「共感した」「ちょっと元気出た」と言ってもらえたとき、
「ああ、自分の経験も誰かの役に立てるんだ」と、じわっと嬉しさがこみ上げてきます。
そして、そんな僕を支えてくれているのが、まさにこのブログを読んでくれている“あなた”です。
読者さんがいること、それだけでこのブログには存在する意味があると思っています。
もし今、あなたが「なんかしんどいな…」「また頑張れるかわからないな…」と思っているなら、
どうか、焦らずに、ここに戻ってきてください。
ここには完璧な成功談はありません。でも、転んで、泣いて、立ち上がって、また転んで、それでも歩いてきた“等身大の記録”があります。
誰かの立派なノウハウより、同じ地面を這いつくばっていた誰かの声が、
時に一番の力になることがあると信じています。
僕の記録が、あなたの明かりの一つになれたら、こんなに嬉しいことはありません。
まとめ
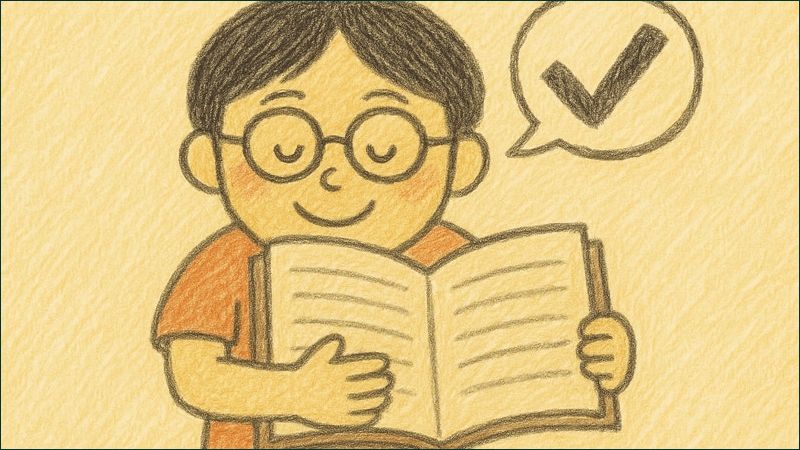
ブログって、決してラクなものではないけれど、そのぶん「確かな力」がついていくツールだと思っています。知識も経験もなかった僕が、試行錯誤のなかで“自分の道”を探し続けてこれたのは、
まさにこの「書く」という営みによって、心も人生も少しずつ整っていったからです。
僕のような、どこにでもいる普通の人間でも、コツコツ続けていけば“積み重ね”が人生をちょっとずつ変えてくれる。それを、9年間の試行錯誤を通して、ようやく実感できるようになりました。派手な実績がなくても、毎日10分でも手を動かし、言葉を綴っていくことで、
少しずつ見える景色が変わり、気づけば自分の価値観や選択の軸も変わっていました。
たとえば、ブログを始めた当初は「稼げたらいいな」という気持ちが一番でしたが、
今は「誰かの小さな救いになれたらいいな」と思えるようになっています。
それはおそらく、たくさん迷って、遠回りして、それでも書くことを続けてきたからこそ見えてきた変化です。
このプロフィールが、もしあなたの背中をそっと押せたなら、それだけで僕の9年間には、意味があったと思えます。何もすごいことは言えないけど、「大丈夫、一緒にやっていこう」とだけは心から言えます。
これからも、ゆるくて、でも確かに前進していけるようなブログを目指して、あなたと一緒に歩んでいけたら嬉しいです。その過程で出会えた気づきや工夫、ちょっとしたつまずきも、正直に全部シェアしていきます。
どうぞよろしくお願いします!