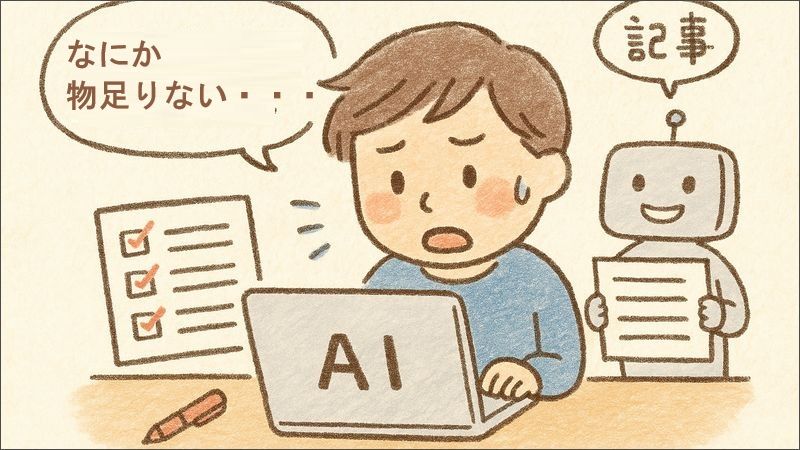
AIで記事を書くようになってから、「うわ、これもう人間いらないじゃん…」って一瞬だけ本気で思った時期がありました。
キーワードを入れて、ちょっと指示をしてあげるだけで、昔は3時間かかっていたような記事の“形”が、数分でどーんと出てくるんですよね。
でも、ある日ふと気づいたんです。
「このスピード感、すごいんだけど…記事として“心に残る感じ”が薄いな…」って。
アクセスは来る、検索順位も悪くない、それでも読んだあとに自分ですら何も残っていないような不思議な空っぽ感があって、モヤモヤが消えない時期がしばらく続きました。
そのときにハッキリわかったのは、AIが作ってくれるのは“情報としての文章”であって、“誰かの胸の中に届いていく言葉”は、やっぱり人間が仕上げないとダメなんだ、ということでした。
それ以来、僕は「AIに全部任せる」のをやめて、「AIに7割やってもらって、最後の3割で人間が魂を入れる」というスタンスに切り替えました。
今回は、そんな試行錯誤の中で固まってきた「AI記事を30分で公開まで持っていくときの、人間の仕上げポイント」を、かなり具体的にお話していきます。
「わかる、それ私もやってる」「うわ、そこ盲点だった…」とどこか一つでも心当たりがあったら、次の記事からこっそり取り入れてみてくださいね。
AI任せにしたときに訪れた「静かな違和感」と空っぽ感
AIを使い始めた頃の僕は、正直テンションがものすごく上がっていました。
仕事が終わって家族が寝たあと、眠い目をこすりながらパソコンに向かって、「よし、今日は2記事いけるかな…」と気合を入れていたあの頃と比べたら、今はAIが一瞬でたたき台を作ってくれる。
「これはもう、量産モード入るしかないでしょ」と本気で思っていました。
ところが、です。
数日たってから、そのAI任せで投稿した記事を読み返してみたときに、胸のあたりがスッと冷たくなったんですよね。
「何も間違っていないし、内容もちゃんとしてる。だけど、なんか、自分のブログじゃないみたいだな…」と。
たとえるなら、ものすごくよくできたマニュアルを読んでいる感じです。
正しさはあるけれど、血の通った温度がない。
それまで自分で、眠気と戦いながら絞り出すように書いてきた拙い記事のほうが、正直、“自分の言葉”としては強く残っていることに気づいてしまったんです。
そこから、「これはAIがダメなんじゃなくて、僕の使い方が“惜しい”だけなんだろうな」と思うようになりました。
AIを便利な道具としてだけ使うんじゃなくて、ちゃんと“相棒”として育てていくにはどうしたらいいか。
そう考えたときに出てきたのが、「AIのあとに人間が必ずチェックする3つの視点」でした。
チェック1:感情の温度を整える「読み手の心の温度計」
AIの文章は「正しいけど、冷蔵庫の中みたい」
AIが作る文章って、とにかく整っています。
論理の流れも破綻していないし、情報もまんべんなく入っている。
でも、ときどき読むたびに、「うん、正しいんだけどさ…」と、どこか距離を感じることが多いんですよね。
特に目につきやすいのが、「~することが重要です」「~する必要があります」といった、冷静だけれど上から目線に感じられやすい言い回しです。
読む側がちょっと弱っているとき、こういう表現って心にズシッと乗っかってきてしまうんですよね。
「必要なのはわかってるんだよ…でもしんどいからググってるんだよ…」みたいな。
“正しさ”に少しだけ“やさしさ”を足す
そこで僕は、AIの文章をチェックするときに、「この言い方、今の自分が読者だったらどう感じるかな?」と想像しながら、言葉の温度を調整していきます。
「~する必要があります」は「~しておくと、あとがすごくラクになりますよ」に変えてみる。
「~することが重要です」は「ここだけ意識しておくと、失敗しにくくなりますよ」に言い換えてみる。
意味としては同じなんです。
でも、「命令されている感じ」から、「隣に座って教えてもらっている感じ」に変わるだけで、読後感がかなり変わってくるんですよね。
僕が意識しているのは、「夜中にスマホ片手に不安で検索している自分」に向けて書くイメージです。
その自分に対して、先生みたいに正しさだけを並べるのか。
それとも、「わかるよ、その気持ち」と一度寄り添ってから、そっと提案してあげるのか。
この違いが積み重なっていくと、記事全体の空気がふんわりやわらかくなっていきます。
チェック2:読み手の視点に戻る「過去の自分インタビュー」
“わかっている側”の文章は、あっという間に難しくなる
アドセンス歴が長くなればなるほど、どうしても陥りやすいのが「説明が一段飛んでいる文章」です。
自分の中では当たり前になっていることが増えてくるので、「ここって前提として伝えなくてもわかるでしょ」と思い込んでしまうんですよね。
僕も外注化やAI活用についての記事を書いているとき、ふと読み返してみて「いや、これ初心者のときの自分に読ませたら、絶対にポカンだな…」と思ったことが何度もあります。
“レバレッジが効く”“スケールする”なんて表現も、その典型ですよね。
アドセンス界隈やビジネス系の発信では日常でも、普通の人からしたら宇宙語みたいなものです。
「昔の自分に説明するつもりで」書き直す
そこで僕がやっているのが、記事を読み返しながらの“過去の自分インタビュー”です。
「これ、アドセンス始めた頃の自分が読んで理解できるかな?」
「システムエンジニアじゃない自分の友だちが読んでも、イメージできるかな?」
たとえば、「外注化するとレバレッジが効いてスケールしやすくなる」という一文があったとします。
これを僕は、「外注さんに記事を書いてもらえるようになると、自分一人で書ける記事数の限界を越えやすくなって、ブログが育つスピードがグッと上がるんですよ」に書き換えます。
同じことを言っているのに、「映像として想像できるかどうか」がまったく違いますよね。
その“映像が浮かぶかどうか”をチェックするのも、人間の役目です。
僕は娘に何かを説明するときの顔を思い浮かべながら、「これ、娘にも説明できる言葉かな?」という基準で言い換えることが多いです。
誰か一人の顔を具体的に思い浮かべて書き直すと、表現が一気にやさしくなっていきます。
チェック3:検索の向こう側にいる「今の感情」にちゃんと答えているか
同じキーワードでも、心の中身は違う
AIに記事を書いてもらうと、ときどき「情報的には間違っていないのに、読者のモヤモヤが晴れていない記事」ができあがることがあります。
その原因のひとつが、「検索の裏にある感情」をちゃんと拾い切れていないことだと感じています。
たとえば、「AI 記事作成 こわい」で検索する人と、「AI 記事作成 コツ」で検索する人。
同じ“AI記事作成”というテーマだけど、前者は「やってみたいけど不安で怖い人」、後者は「すでに始めていて、もっと効率を上げたい人」ですよね。
求めている言葉も、全然違ってきます。
なのに、その違いを意識せずにAIに丸投げすると、「とりあえず全部載せときました」みたいな記事ができあがってしまう。
どこにも間違いはないのに、“誰の心にも深く刺さらない”不思議な文章が誕生してしまいます。
「この記事を読み終えたとき、どんな気持ちになってほしい?」
そこで僕がやっているのは、記事の最後の段階で、「この記事を読み終わった人に、どんな気持ちになってもらえたら成功かな?」と自分に問いかけることです。
不安で検索してきた人には、「あ、なんとかなるかも」と少し肩の力が抜けるような感覚を持って帰ってほしい。
やる気に満ちて検索してきた人には、「よし、これで一歩進めそうだ」と背中を押された感覚を持ってほしい。
今回のテーマで言えば、AI任せの記事にどこかモヤモヤを感じている人に、「ああ、最後の5~10分でできる“人間の仕事”ってこういうことなんだ」と気づいてほしいし、「じゃあ次の記事から、ちょっとやってみようかな」と前向きな一歩を踏み出してもらえたら、それで大成功だと思っています。
AIの出してくれた文章をただ整えるのではなく、「この人の心の中にこの言葉を届けたい」という一点に向かって文章を整えていく。
そこには多少の時間はかかりますが、その時間こそが“自分のブログらしさ”を取り戻してくれる、大事な作業なんだろうなと感じています。
30分で記事を仕上げるためのリアルな感覚と、あきらめない工夫
AIを使っていても、人間の仕上げをしっかりやろうとすると、最初はどうしても時間がかかります。
僕も、はじめのころは一記事に1時間以上かかっていましたし、「これ本当に時短になってるのかな…」と若干の迷子状態になっていた時期があります。
でも、「AIに任せるところ」「人間がしっかりやるところ」の境界線が見えてきてから、一気に楽になりました。
AIには、構成のたたき台と、情報をまとめる作業を任せる。
その上に、人間が「感情の温度調整」「読者目線のすり合わせ」「検索の裏にある気持ちへの答え」を乗せていく。
この役割分担を意識するようになってから、30分という時間の中でも、記事に温度を込める余裕が生まれるようになりました。
体感としては、構成とAIの下書き生成に15分、そこからのリライトと感情調整に10分、最後のタイトル調整やまとめの微調整に5分という感じです。
もちろん、その日によって前後はしますし、「これは絶対に丁寧に書きたい」と思う記事にはもっと時間をかけることもあります。
ただ、「毎回120点を狙う」のではなく、「昨日より1ミリでも自分らしい記事になったらOK」という基準を自分の中に置いておくと、続けるのがすごく楽になりました。
まとめ
AIを使うようになって、記事を書くハードルは確かに下がりました。
昔のように、真っ白な画面を前にして「何から書けばいいんだ…」と固まってしまう時間は、ほとんどなくなりました。
それ自体は、本当にありがたい変化だと思っています。
でも、その一方で、AIだけに頼ってしまうと、いつの間にか“自分の声が消えたブログ”ができあがってしまう危険もあります。
どの記事もそれなりに整っているのに、どれも同じ味がして、「このブログじゃなきゃ読めない理由」が薄くなってしまう。
だからこそ、最後の5~10分でいいので、「人間の仕上げポイント」を意識してみてほしいなと思っています。
感情の温度を整えて、「今のあなたに話しかけているよ」という空気を文章に乗せること。
専門用語や難しい言葉を、昔の自分や家族にも伝わるレベルまで噛み砕いてあげること。
そして、検索の裏にある「今の気持ち」に、ちゃんと言葉で寄り添ってあげること。
AIが文章を作り、人が温度と魂を入れる。
その共作のバランスがうまくハマったとき、「あ、これだ。こういう記事を書きたかったんだ」と自分でも思えるような記事が生まれてきます。
もし今、あなたが「AIの記事、便利なんだけど、なんかしっくりこないんだよな…」と感じているなら、きっとそれは“あなたの感性がちゃんと働いている”サインです。
その違和感は、無視しなくていいものです。
むしろ、そこにこそ、あなたのブログの個性や、読者から選ばれる理由が眠っています。
次にAIで記事を作るときは、ぜひこの記事で話した3つのチェックを、最後の仕上げにそっと足してみてください。
きっと、同じAIを使っているのに、「あなたにしか書けない記事」に近づいていきますよ。
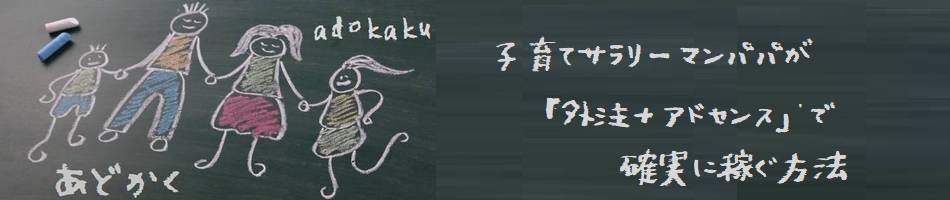
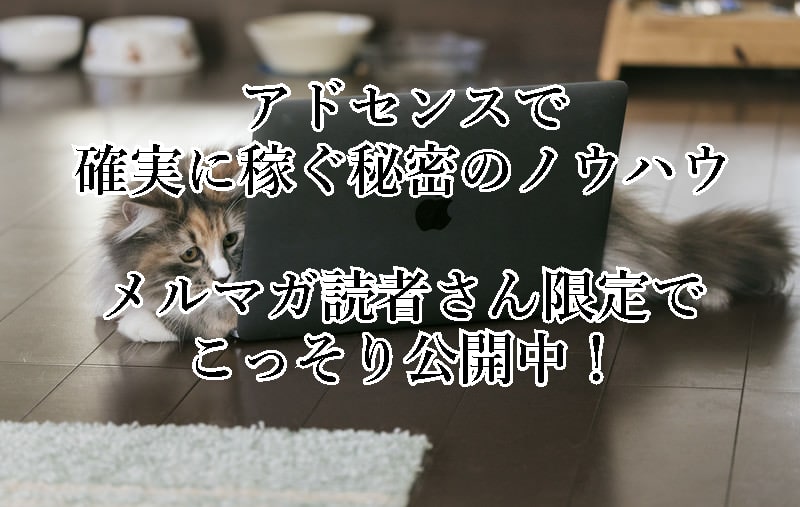


コメント