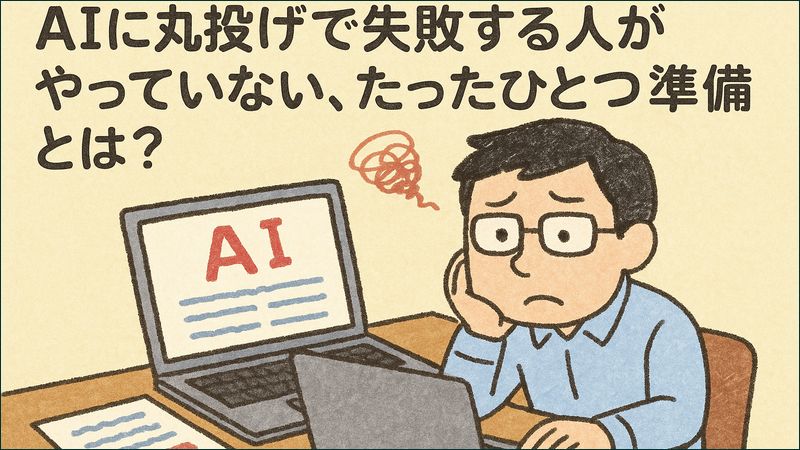
ブログにAIを取り入れる人が増え、「記事作成の効率が上がった」「もう自分で書かなくていい」といった声もよく聞くようになりました。
実際、僕自身もChatGPTに出会ったときは「これは革命だ」と感じ、これまで何時間もかけていた記事作成が一気に短縮できると思っていました。
しかし、AIに任せた記事をいくつか投稿してみたものの、アクセスは伸びず、検索順位も思ったように上がらない。
「なぜ?」という疑問が残りました。
記事の構成は整っているし、読みやすさも悪くない。
それでも読者に届かない。
冷静に読み返して気づいたのは、内容に“体温”が感じられないということでした。
誰の悩みに寄り添っているのか、どんな思いで書かれているのかが見えないのです。
特に、健康や生活、お金に関するようなテーマでは、信頼性や共感が非常に大切です。
そうした分野では、AIがいくら流暢に書いても「読者が納得して行動につなげる」ための要素が抜け落ちていると、結果につながりにくくなります。
今回は、そんな僕自身の失敗談をもとに、AIで成果を出すために欠かせない「考えてから丸投げする」という視点について、具体的にお話ししていきます。
なぜAIに任せたのに成果が出なかったのか
AIに記事を丸ごと任せられる時代になり、多くの人が「これでブログ運営が一気に楽になる」と期待しています。
僕自身もそうでした。
ChatGPTを導入した当初は、思考のプロセスをすっ飛ばして、ただキーワードだけを入力して記事を出力し、そのまま投稿していたんです。
でも、いくら記事を量産してもアクセスは増えず、アドセンス収益も横ばい。
内容は間違っていないはずなのに、読者の反応がまるでありませんでした。
その原因は、「記事が誰のために書かれているのかが不明確だった」という点にあります。
読者の悩みに寄り添っていない、気持ちに共感していない、単に“それっぽい文章”が並んでいるだけ。
特に健康や家計、教育、子育てなど生活に密接するテーマでは、読者は安心感や信頼性を求めています。
YMYLに該当する記事であればなおさら、情報の出どころや文脈、配慮のある語り口が求められます。
AIに丸投げしてもうまくいかないのは、文章そのものの問題ではなく、「読者にとって必要な視点が抜け落ちているから」です。
AIの性能を最大限に活かすには、記事の“芯”をまず人間が与える必要がある。
そう痛感した瞬間でした。
成功する人は「丸投げの前に考えている」
AIで成果を出している人たちは、決して「ただ丸投げしているだけ」ではありません。
むしろ、AIに任せる前の“準備”に力を注いでいるのです。
記事を仕上げるプロセスのうち、どこを人が担い、どこをAIに任せるか。
成功している人ほど、この役割分担が明確です。
たとえば、記事を書く前に
「このキーワードで検索する人はどんな悩みを抱えているか?」
「どんな情報を求めているか?」
「どうすれば読み終わったあとに安心できるか?」
といった“読者の背景”を深く想像しています。
そのうえで、見出し構成を簡単に組み立てたり、導入文に盛り込むべき共感ポイントを考えたりする。
つまり、記事の設計図を人間が描き、その設計図に基づいてAIが文章を仕上げるという流れです。
この流れを踏めば、文章の一部に多少AIらしさが残っていても、読者に「自分ごと」として伝わる記事になります。
特にYMYLの領域では、「この人はちゃんと考えて書いている」と思ってもらえることが信頼につながり、離脱率や検索評価にも影響します。
AIは魔法のツールではありません。
しかし、考えたうえで使えば、最高のライティングパートナーになります。
成功している人は、そのことをちゃんと理解しているのです。
AIは外注と同じ。成果は「指示力」で決まる
AIに記事作成を任せるということは、ある意味“外注”と同じ行為です。
人間のライターに依頼する場合も、「おまかせで」と丸投げすれば、無難だけど刺さらない記事が返ってくることがありますよね。
逆に、「誰向けに、どんな悩みに答えたいのか」を具体的に伝えることで、ぐっと読者の心に届く内容に仕上がる。
それとまったく同じです。
AIも指示次第で仕上がりが大きく変わります。
「キーワードだけを渡す」
「とりあえずこのテーマで書いて」
といった曖昧な指示では、文章は整っていても、読者にとって必要な答えが得られない記事になってしまいます。
特に、健康・子育て・お金・教育といったYMYL領域では、不安をあおる表現や根拠のないアドバイスが含まれると、信頼性を損なうだけでなく、ブログ全体の評価にも悪影響を与えるリスクがあります。
だからこそ、
「どんな背景をもつ読者に向けて」
「どのようなトーンで」
「どこに注意して」
など、意図や感情、構成の方向性をきちんと伝える指示力が、AI活用では成功のカギになります。
信頼される記事を生むには、まず自分自身が“誰に何を伝えたいのか”を言語化できるようになることが重要なのです。
まとめ:AIを使いこなす人は“考えたうえで丸投げしている”
AIに記事作成を任せるのは、たしかに画期的で、時間や手間を大きく削減できる可能性を秘めています。
しかし、「AIにすべてを任せれば勝手に稼げるようになる」と考えてしまうと、かえって遠回りになりかねません。
特に、読者の生活や健康、教育、お金に関わるようなテーマでは、読者の悩みにきちんと向き合い、安心できる情報を丁寧に届けることが強く求められます。
これは、YMYLジャンルであれば当然のことです。
AIで成果を出している人たちは、例外なく“丸投げの前に考える”というステップを大切にしています。
記事のターゲット、検索意図、構成、トーンなどを事前に整理し、AIには「その設計に基づいて文章を仕上げてもらう」感覚です。
これができると、AIはただの便利なツールではなく、共に信頼される記事を生み出すパートナーになります。
逆に、何も考えずにキーワードだけで記事を生成すると、「誰のための記事なのか」「何を伝えたいのか」がぼやけてしまい、読者の心に届きません。
AIは便利ですが、使い方を間違えれば“質の低い情報”を量産する危険性もあります。
だからこそ、人間が担うべき“考える”部分を意識的に残すことが、これからの時代に求められるAI活用の本質ではないでしょうか。
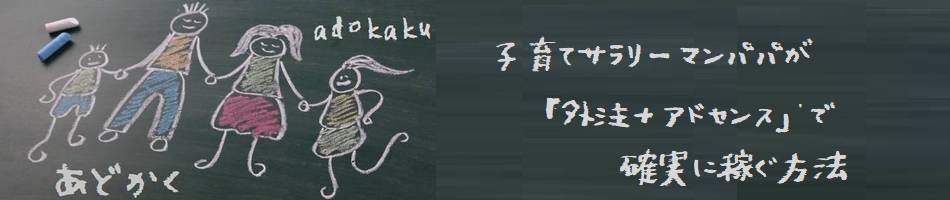
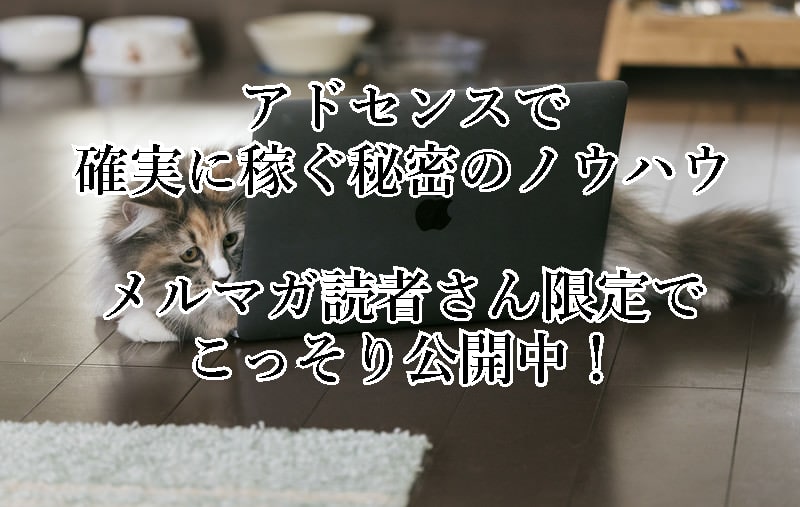


コメント