
ブログを始めて9年。
外注を試したり、夜中にひとりで記事を直したり、何度も「もうやめようかな」と思いながら続けてきました。
収益は少しずつ伸びているものの、納期の遅れや記事の質のバラつきに悩まされる日々。
深夜にパソコンとにらめっこしていると、リビングでは息子がゲームをしていて、娘が勉強をしている。
その光景を横目に「この時間を家族と一緒に過ごしたいのに」と心のどこかで思いながらも手を止められない自分に、何度もモヤモヤしていました。
そんなときに出会ったのがAI記事作成。
正直、最初は怖かったです。
AIなんて使ったらブログが機械的になるんじゃないか、手抜きだと思われるんじゃないか、そんな不安が頭をぐるぐるしました。
でも思い切って1記事試してみたら、意外にも記事は自然で、自分の体験談や感情を加えることでむしろ温かい記事に仕上がったんです。
そこから少しずつAI記事を増やしていくと、作業時間が減って家族と過ごす時間が戻り、ブログ更新も安定していきました。
AIは人間の代わりではなく、あくまで自分の分身として一緒に記事を作ってくれる存在なんだと気づいた瞬間でした。
AI導入をためらった理由
「AIで記事を作る時代が来た」
そんな話を耳にするたびに、正直なところ僕はひるんでいました。
ブログ歴9年。
これまで外注さんと試行錯誤してきたし、自分でキーワードを考え、構成を作り、夜な夜な記事を手直ししてきた日々には、それなりの「汗」と「時間」と「想い」が詰まっています。
だからこそ、AIに記事を任せるというのは、自分の大切にしてきたものを「放棄する」ような気がして、怖かったんです。
読者との信頼関係が壊れるかもしれないという不安
僕が一番悩んだのは、「読者にどう思われるか」でした。
「AIで作った記事ってバレたらどうしよう。」
「機械っぽい文章だと信頼を失ってしまうんじゃないか。」
そんな不安がずっと頭の中でぐるぐるしていました。
ごちゃまぜブログとはいえ、読者の悩みにちゃんと寄り添いたいと思って書いてきました。
だからこそ、AIで生まれた“どこか冷たい文章”を読者が見抜いてしまったら、その信頼が一気に壊れてしまう気がしたんです。
特に僕のような、パパ目線での体験談を重ねて記事を書くスタイルの場合、文章にこもる「人の温度」が読者とのつながりになっている感覚がありました。
だからこそ、そこをAIに任せることに、抵抗を感じずにはいられませんでした。
外注の限界と自分の限界
ただ、その一方で現実もありました。
外注さんの記事はありがたい。
でも、納期が遅れたり、構成とズレた記事が納品されたり。
結局「これなら自分でやった方が早いかも」と思うような手直しに、時間も気力も削られていました。
しかも夜中までパソコンに向かって修正作業をしていると、翌朝の出勤が本当にきつい。
小6の息子に「パパまだやってるの?」と言われてハッとする瞬間があったり、中3の娘と話す時間が減ってしまったことに、心のどこかで罪悪感が募ったり。
「このままじゃ、ブログを続ける意味がなくなるかもしれない」
そんな気持ちになっていた時期だったからこそ、AIの存在が妙に心に引っかかったんです。
罪悪感との戦い
AIに頼るということは、自分の努力や経験を否定することになるんじゃないか。
誰かの手を借りるのとは、また違った「逃げ」なんじゃないか。
そんな風に思っていました。
でも、同時に「自分だけで全部抱えることの限界」も、僕の中でははっきりと見えてきていました。
無理して続けて、心も体もすり減らして、それで得られるのが「達成感」ではなく「疲労感」なら、それはきっと続ける意味を見失うサインなんだと。
だから、迷いながらも「AIに任せてみる」という選択肢を、僕は一度受け入れてみることにしたんです。
最初の一歩とAIの衝撃
ずっと迷っていたけれど、ある晩とうとう「やってみよう」と思えたんです。
きっかけは、外注で頼んでいた記事が2週間も遅れ、しかも届いた原稿の内容がテーマとまったくズレていたことでした。
「もう限界かもしれない…」
そう思って、以前から気になっていたChatGPTを開き、恐る恐る初めてプロンプトを打ち込みました。
「記事タイトルはこれで、読者はこんな人で…」
自分の頭の中を文章で伝えるのって、最初はすごく難しくて、「こんなので本当に記事になるのかな」と不安しかありませんでした。
数秒後に出てきた“それっぽい文章”に驚いた
でも、画面に表示された文章を読んだ瞬間、思わず「え?」と声が出たんです。
流れるような構成、結論から始まる展開、見出しごとの要点整理…。
たしかに、少し無機質ではあるけれど、骨組みとしては十分すぎるクオリティでした。
僕はすぐにその文章に、自分の体験や言葉を重ねていきました。
息子とのエピソードを入れてみたり、自分が感じた葛藤を差し込んだり。
するとどうでしょう。
まるで自分が書いたような記事に、少しずつ仕上がっていく感覚がありました。
それまで「AIは冷たい」と思い込んでいた自分の中の偏見が、音を立てて崩れていくのを感じました。
失ったものではなく、取り戻せたもの
AIを使うことに対して、僕はどこかで「自分の価値が下がるんじゃないか」と思っていたのかもしれません。
でも実際は逆でした。
構成を考える時間が減った分、家族との会話が少しだけ増えました。
息子のゲームの話に付き合ったり、娘の高校選びの悩みに耳を傾けたり。
そうした“当たり前の時間”を取り戻せたことに、何よりも価値を感じたんです。
記事を書くことが目的だったはずなのに、気がついたら「自分の暮らしを整えるために書いている」と思えるようになっていた。
あのときの小さな一歩が、今の自分を作ってくれた気がしています。
成功のカギは丸投げしないこと
ChatGPTを使うようになって、最初に感じたのは「楽になった」ということでした。
構成も見出しも、それなりの本文も、数秒で出てくる。
それだけ聞くと「もう人間いらないじゃん」と思うかもしれません。
実際、僕も最初は「このまま投稿できちゃうんじゃないか?」と甘い期待を持っていた時期もあります。
でもね、そうやって“そのまま”出した記事がどうなったかというと…正直、読まれませんでした。
アクセスも伸びないし、なぜか読了率も低い。
見た目は整っていても、中身が「伝わらない」記事になっていたんです。
AIには“空気”が読めない
これは僕の感覚なんですが、ChatGPTって文章のロジックはすごくしっかりしてるんですよね。
でも、
「今このテーマで悩んでる人は、どんな気持ちでこのページを開いているか」
「この言い回しって、なんか冷たく感じるかも」
そういった“空気”の部分までは汲み取ってくれません。
たとえば、外注さんなら人間同士だから意図が伝わったり、ちょっとしたニュアンスが読み取れたりするけれど、AIは本当にこちらが指示したことに忠実なんです。
だからこそ、「指示の出し方」や「後からどこに自分の気持ちを足すか」が、めちゃくちゃ大事だと気づきました。
自分の言葉で仕上げることで“魂”が宿る
あるとき、AIが書いた本文を一部だけ直してみたんです。
たった2~3行、自分の体験談を入れてみたり、「僕はこう思う」と主観で語ってみたり。
すると、不思議なくらい記事が“生き返る”ように感じたんですよね。
読者からも「この記事すごく共感しました!」とコメントが来て、Analyticsの滞在時間もぐんと伸びていました。
このとき、「AIが作るのは“骨組み”、命を吹き込むのは自分」なんだと、本気で実感しました。
記事が読まれるかどうかは、情報の正確さだけじゃなくて、
どれだけ“人の気持ち”がこもっているかが重要なんです。
だから僕は、今でも記事の仕上げは必ず自分の手でやるようにしています。
少し遠回りに思えるかもしれないけれど、それが結果として「読まれる記事」「信頼されるブログ」につながっていると感じています。
AIとの信頼関係が生まれた瞬間
最初はただの道具だったんです。
ChatGPTは、早く、正確に、そこそこの文章を出してくれる便利な存在。
でもそれ以上でもそれ以下でもない、そう思っていました。
けれど、ある1本の記事で考えが変わったんです。
テーマは、家族で初めて行ったキャンプの思い出を交えた記事でした。
子どもが火を起こすのに苦戦して、やっとついた火に喜んでいたあのシーン。
僕にとってはただのキャンプレポートじゃなくて、「一生残したい記憶」だったんです。
AIが“形”をつくってくれたからこそ思い出に向き合えた
このときも、まずChatGPTに構成と文章を任せました。
すると、「なるほど、こういう流れにすれば読者に伝わるのか」と新たな視点が見えてきたんです。
僕がただ主観的に語ろうとしていた出来事を、ちゃんと読者目線で整えてくれていた。
その文章をベースに、僕は自分の思いをひとつひとつ丁寧に重ねていきました。
するとどうでしょう。
AIだけでは出せなかった“あたたかさ”と、僕ひとりでは整理できなかった“伝わりやすさ”が、絶妙にかみ合った記事ができあがったんです。
その記事を公開したあと、久しぶりにコメントをもらいました。
「同じように子どもとキャンプしたことを思い出して涙が出ました」
たった一言でしたが、そのメッセージを読んだとき、心が震えるような感覚がありました。
信頼は「任せすぎず、信じること」から生まれる
AIに全部任せるのではなく、でも“信用して使ってみる”という距離感。
そのバランスが、自分の中で少しずつ掴めてきたのがこの頃でした。
完全にコントロールしようとすると、どこかギクシャクするし、
逆に丸投げすると自分の気持ちが乗らない。
だからこそ、AIの得意なところに任せて、自分は“感情”と“信念”を込める。
まるで相棒のように、役割を分けて一緒に記事をつくっていく感覚。
そんな“信頼関係”のようなものが芽生えたとき、
僕はようやく「ブログを続けていけるかもしれない」と思えるようになったんです。
あの孤独だった作業の時間が、ちょっとだけ楽しくなった気がしました。
AI時代でも伝わる文章には“人間らしさ”が必要だった
AIがどんどん進化して、文章も画像も、下手したら動画までも機械がつくる時代。
そんな流れのなかで「じゃあ、人間の出番って何なんだろう」と立ち止まった瞬間が、僕にはありました。
あるとき、ChatGPTだけで1記事すべて作ってみたことがあります。
構成も、本文も、体験談っぽい一文までAIに任せてみたんです。
それっぽく仕上がった見た目にちょっと安心しつつ、投稿ボタンを押しました。
でも数日経っても、その記事は読まれなかった。
検索順位も上がらず、読了率も低く、SNSでも反応がない。
「なぜ?」と思って自分で読み返してみて、気づいたんです。
あの文章には、“僕の言葉”がなかった。
読者は“正しい情報”より“誰が書いたか”を見ている
もちろん、内容は間違っていないし、文章としての流れもスムーズ。
でも、そこに「人間の揺れ」や「経験に裏打ちされた説得力」がなかったんですよね。
読者って、ただ情報を集めたいんじゃない。
“自分の悩みをわかってくれる誰かの声”を求めてる。
たとえば「子育てが大変」と一言で言っても、それを
「昨日の夜、寝かしつけに1時間かかって、やっと寝たと思ったら下の子が泣き出した」
と書くだけで、読者の共感度って一気に変わるんです。
それは、AIにはどうしても再現できない“生きた記憶”からしか出てこないもの。
だからこそ、情報の正確さ+人間のリアルな感情があって初めて、
読者の心に届く“伝わる文章”になるんだと、身をもって実感しました。
AIと心地よく共存するという選択
それからは、僕の中でAIの立ち位置が変わりました。
「自分の代わり」ではなく「自分を助けてくれる右腕」。
疲れてるときに構成を考えてくれたり、
言いたいことを整理してくれたり、
ときには言葉が出てこないときにヒントをくれる。
でも最後に「この一文は、僕だからこそ書ける」と思えるひとことを入れることで、
その記事は初めて“息をする”んです。
そうやって、AIと共に作った記事たちが、少しずつ読者の反応をもらえるようになっていきました。
SNSでの共感の声や、検索順位の上昇、直帰率の低下。
それは、僕にとって「AI時代の人間の価値って、やっぱり“感情”なんだ」と確信する出来事でした。
まとめ:AIと歩く、等身大の自分らしいブログ運営へ
ChatGPTを導入すると決めたとき、僕の中には不安も怖さもありました。
「これって手抜きじゃないか?」「人間らしさが消えてしまわないか?」
そんな葛藤の中で始めたAIとのブログ運営は、決して“楽になった”だけの話ではありません。
確かに、記事の構成や下書きをAIに任せることで、作業の負担は減りました。
でも、それ以上に大きかったのは「自分の言葉や感情の価値」に、もう一度気づけたことです。
AIは素早く、正確に、整った文章を出してくれます。
だけど、そこに“誰かの気持ちを支える温度”を宿すのは、やっぱり人間の言葉なんだと思います。
読者の心に寄り添えるのは、自分がかつて悩んだこと、迷った経験、乗り越えた想いがあるからこそ。
だからこそ、AIは「敵」でも「代わり」でもなく、「共に歩く相棒」であるべきなんだと思います。
AIの得意な部分に助けてもらいながら、自分にしか書けない体験と想いを丁寧に重ねていく。
それが今の僕にとって、一番自然なブログの形です。
AIの力を借りたからこそ、家族との時間が戻り、心に余白が生まれ、ブログを“続けたい”と思えるようになりました。
これからも試行錯誤は続くと思います。
けれど、それもまた“僕らしさ”の一部として、読者とゆっくり向き合っていけたら。
そんな風に思えるようになった今、あのとき一歩踏み出して、本当によかったと心から思っています。
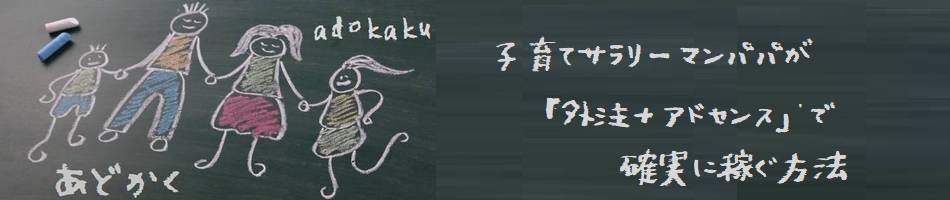
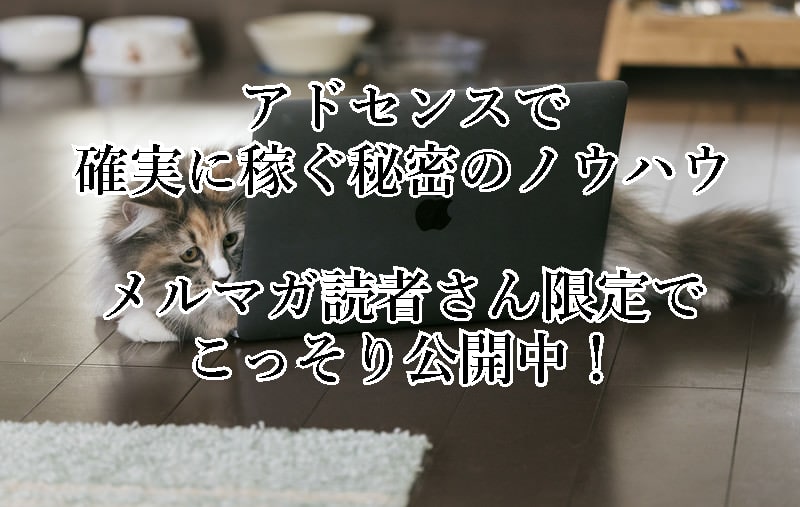


コメント