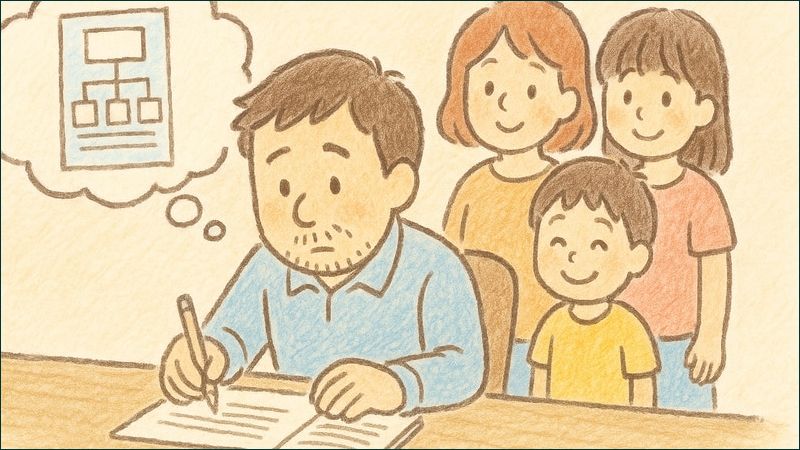
こんにちは!かすかくです。
僕はアドセンス歴9年目。
でもお恥ずかしながら、この9年間ずっと「中途半端な実績」で足踏みをしてきました。
記事もたくさん書いてきましたし、ライティングの勉強もしました。
それでも、なぜか結果が出ない。
そんな長いトンネルのような時期を抜けるきっかけになったのは、意外にも「ライティング」ではない、ある部分の改善でした。
今日は、その体験談をお話します。
もしあなたが「頑張っているのにアクセスが伸びない…」と感じているなら、きっと参考になるはずです。
なぜ、ライティングを磨いても結果が出なかったのか
僕はずっと「稼ぐにはライティングスキルが大事だ」と信じていました。
だから、時間を見つけては文章の勉強をし、記事を書くたびに推敲を重ねていました。
おかげで昔より読みやすい文章は書けるようになったと思います。
外注さんの記事も、しっかりチェックして修正していました。
でも、アクセスの伸びはほんの少し。
正直、何が悪いのか、自分でもわからなくなっていました。
転機は外注記事のやりとりで気づいた
そんなある日、外注さんに「とりあえずキーワードと文字数だけ指定」して記事を依頼しました。
納品された記事を読んだ瞬間、「あれ?」と違和感がありました。
キーワードは入っているし、文法的にもおかしくない。
でも、読んでいて全然ピンとこないし、役に立つ感じがしない。
読者が欲しい情報が順番通りに並んでいないし、途中で答えが出てしまったり、逆に結論がボヤけていたりするんです。
そこでハッとしました。
「これ、昔の自分が書いていた記事と同じだ…」
「設計図」を変えたら、アクセスが伸び始めた
そこで僕は、記事を書く前に「設計図」を作るようにしました。
記事構成とも呼ばれるこの設計図は、
読者の悩みや疑問を順序立てて解決していくための「地図」です。
やり方はシンプルです。
記事設計の基本ステップ
読者のペルソナを明確にする
例えば、「子育て中のママが、短時間で夕食を作りたいと思っている」など。
読者の悩みを書き出す
「時短レシピが知りたい」「栄養バランスも気になる」など、箇条書きでOK。
悩みが解決する流れを考える
どの順番で読めば、ストレスなく理解できるかを決める。
見出し案を決める
H2、H3にどんな見出しを置くか、先に決めておく。
この流れを意識してから、外注さんへの指示も具体的になり、AIに記事を作らせるときも良い記事ができるようになりました。
構成を意識するだけで何が変わった?
設計図を意識した記事を書き始めてから、数字が目に見えて変わりました。
- 平均滞在時間が1.5倍に
- 直帰率が改善
- クリック単価も微増
- 指名検索が増えた
読者の満足度が上がると、リピートも増え、ブログ全体の評価も上がっていくのを実感しています。
「ライティング」も大事。でも、それだけじゃダメ。
もちろん、読みやすい文章を書くライティング技術は必要です。
でも、それだけでは不十分なんだと痛感しました。
いくら良い文章を書いても、読者の知りたいことが順番に整理されていなければ、離脱されてしまう。
構成は、いわば「ライティングを活かすための器」なんです。
あなたも、まずは「設計図」を作ってみませんか?
もし今、アクセスが伸びずに悩んでいるなら、ぜひ一度「設計図」を作るところから始めてみてください。
僕はエクセルで作っていますが、手書きのメモでも十分です。
1記事ずつ、丁寧に読者のゴールから逆算して設計する。
これだけで、ブログの質がぐっと上がります。
それでは、またお会いしましょう!
かすかく
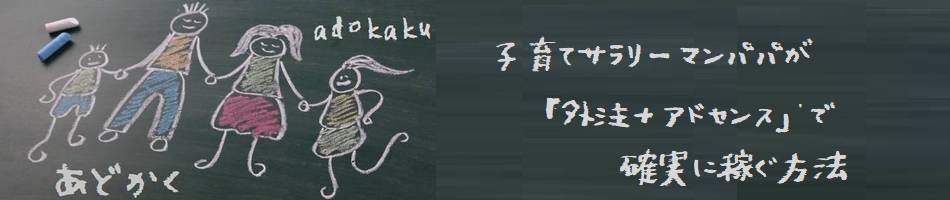
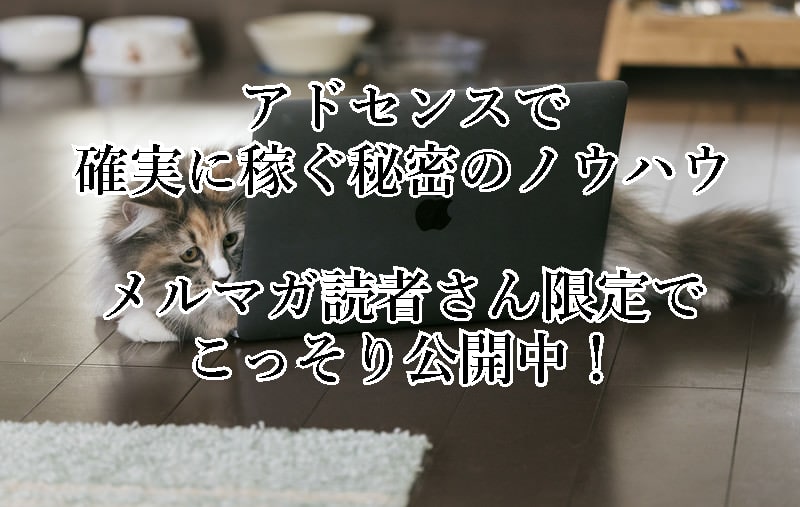


コメント